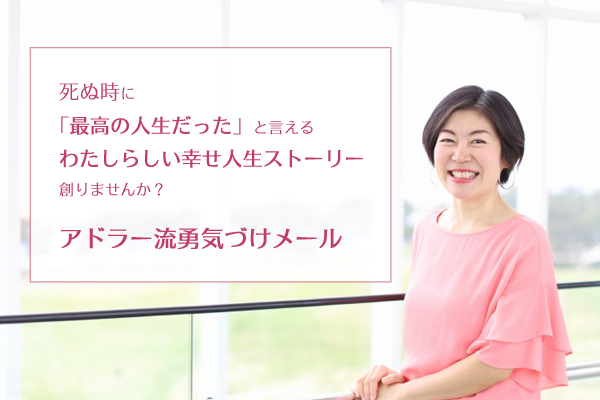以前の毎週水曜朝8時発行の「湯本れいなのアドラー流勇気づけメール」でお届けした内容から抜粋します。
StandFMライブ配信をお聴きくださってる方は、もう何度も耳にしたことかもしれませんが、アドラー心理学でいう「課題の分離」とは、自分の課題と他者の課題を分けて考え、他者の課題に土足で踏み込まず、自分の課題にも他者から土足で踏み込まれないようにすること。
とてもシンプルだし、わかりやすいので、頭ではスグにわかるのに、実際の生活現場ではなかなか実践しにくいのも、この「課題の分離」。
例えば、子どもの部屋が汚くて散らかっている。もう自分で片付けが出来る年齢だけど、ついつい自分(母親)がやってしまう、とか。
子どもが試験前なのに勉強しないで、ゲームしたり動画見たりしている。これまでも勉強不足で点数取れていなかったので「そんなことしてないで勉強しなさい」と口酸っぱく言ってしまう、とか。
子どもが学校で嫌なことを言われた、と子どもからの話を聞いて感じ、すぐに学校や相手の子の親に電話して、どうなってるのか確認してしまう、とか。
子育てされてる方なら「あるある」ですよね?
では、なぜ人は「課題の分離」を頭ではわかっているのに、実践することが難しいのでしょう?
湯本自身も毎日の子育ての現場で「分離」の難しさを実感する中、最近、気付いたコトがあります。
それは・・・
/
他人は自分の心を映し出す鏡だから
\
ということ。
つまりは、子どものことが心配だから、ついつい子どもの課題に踏み込んでしまうと思ってやっているのだけれど、実際は子どもの状態や言動に自分自身を映し出していて、そこに自分の不安・心配・焦りが浮き上がっているから。
過去の自分が失敗したこと
過去の自分が言われたこと
過去の自分がやりたかったけど出来なかったこと
子どもの状態や言動に映し出して、そこに自分の心情が現れていると考えられるのではないかな、と。
「課題の分離」は、子育てのみならず、あらゆる対人関係において活用できる考え方ではありますが、特に子育ての現場で「課題の分離」が難しいのは、親にとって子どもは自分の分身のように思える存在で、子どものことは他人事に思えないからというのもあるかと思います。
子どもが勉強しないで、後々痛い想いをするのがわかっていると、それは他人事ではなく、自分自身がこの先、痛い想いをするように思えるから、何とかしたくなる。
子どもが誰かにいじめられていたら、あたかも自分自身がいじめられているように感じるから、何とか解決したくなる。
因みに、他人のことを他人事ではなく、自分事のように感じるって、一見、アドラー心理学でいう「他人の目で見て、耳で聴いて、心で感じる」という「共感的理解」をしているように思えますが、「共感的理解」はあくまで客観的な立場を保ちつつ、相手の目で見て、耳で聴いて、心で感じることが大事で、自分のメガネを通して自分の心配事のように、見て、聴いて、感じてしまっては、「共感的理解」ではなく「私もわかる~」という「同感」をしているにすぎません。
相手が、他人であれ、自分の子どもであれ、「一人の個人」であり「尊重すべき存在」です。
もし、誰かの状態や言動を見て、その人のことを何とかしなきゃと感じたら、それは自分自身の心情に向き合うチャンス!というサインかもしれません 。
こんな記事が毎週水曜朝8時に届く、「湯本れいなのアドラー流勇気づけメール」は無料購読ができます。登録はこちらから▼▼▼
「自分を変えたい」「望む未来を叶えたい」40代女性のための「嫌われる勇気」「幸せになる勇気」が持てるようになるレッスン
しあわせな人生実現コーチ 湯本レイナ